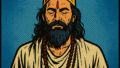荻原規子のデビュー作『空色勾玉』は、日本神話の世界観をもとにした壮大なファンタジー作品でありながら、繊細な心理描写と哲学的な問いかけによって、読む者の心に深く刻まれる名作である。
本記事では、『空色勾玉』の物語構造とテーマ、そして登場人物たちと日本神話における神々との関係を読み解いていく。
物語のあらすじ
物語の舞台は、古代日本を思わせる世界。光=輝(かがやき)の一族と、闇=闇(くら)の一族が存在し、長きにわたり相争っていた時代。物語の主人公・狭也(さや)は闇の一族に生まれた少女でありながら、光の神々を敬い、己の運命に揺れながら成長していく。
ある日、狭也は光の一族の少年・稚羽矢(ちはや)と出会う。彼は、照日王(てるひのおう)の弟であり、姉や兄たちから疎まれている若者。稚羽矢との交流は、狭也に「光」と「闇」という単純な二元論では測れない世界の広がりをもたらしていく。
登場人物と神話上のモデル考察

『空色勾玉』の魅力のひとつに、登場人物たちが日本神話の神々と重ねられている点がある。ここでは主なキャラクターについて、神話との対応関係を考察してみたい。
稚羽矢(ちはや):須佐之男命(スサノオ)
稚羽矢は、「出来損ない」と称され、家族から疎まれた存在として登場するが、物語が進むにつれて本来の力を発揮していく。彼の暴れ者としての側面と、最終的に英雄として再生していく流れは、須佐之男命に通じる。スサノオもまた、姉・天照大神に追放される存在でありながら、八岐大蛇を退治する英雄神である。
照日王(てるひのおう):天照大神(アマテラス)
稚羽矢の姉であり、圧倒的な存在感と威厳を持つ照日王。軍を率い、太陽のように照らす存在である彼女は、まさに天照大神の写し鏡といえる。物語内でも彼女の権威と影響力は絶大であり、全てを照らす光として描かれる。
月代王(つきしろのおう):月読命(ツクヨミ)
照日王の弟であり、稚羽矢の兄にあたる月代王は、冷静沈着で静かな存在感を放つ。神話上のツクヨミもまた、月の神として知られており、アマテラスと対をなす存在である。ツクヨミが神話の中で比較的影の薄い存在とされるのと同様に、月代王も物語の中では抑制された性格でありながら、要所で大きな影響を及ぼす。
狭也(さや):姫神・稲田姫命?
狭也のモデルについては明確な言及はないが、八岐大蛇のいけにえにされた稲田姫命(クシナダヒメ)に重ねられることがある。狭也は闇の巫女として重要な存在であり、神話における「いけにえ」でありながら再生の象徴ともなった稲田姫に通じる。また、水と深く結びつく存在である点も共通している。
光と闇、生と死という二項対立の超克
『空色勾玉』の本質的なテーマは、「光と闇」、「生と死」といった対立軸の超克にある。輝の一族が「変若(おち)」という永遠の命を目指すのに対し、闇の一族は死と再生の循環を肯定する。
この対立は、現代に生きる我々にとっても普遍的な問いである。不老不死を求めるテクノロジーの進化と、自然の摂理を受け入れる生命観の対立。そして、個人としての「光」と「影」の両面をどう受け入れるかという心理的葛藤。
狭也と稚羽矢が最終的に選ぶのは、「闇の道」。すなわち、人間としての有限性と死を抱えながら、それでもなお世界を創るという選択である。この選択は、まさに「人間らしさ」の肯定に他ならない。
まとめ:神話を継ぐ者たち
『空色勾玉』は、神話を借景にしながらも、そこで描かれるのは決して「神々」の物語ではない。神々の時代の終焉と、人間の時代の始まり。狭也と稚羽矢は、自らの選択によってその時代の扉を開いていく。
これは、神話を読むすべての現代人に対する問いかけでもある。
——あなたは、光の道を行くか、闇の道を選ぶか?
どちらの道にも、「世界を創る力」が宿っている。